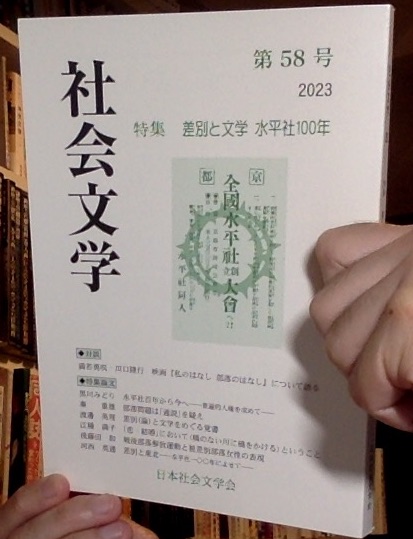新美南吉はぼくの生まれた愛知県の出身である。「ごん狐」があまりにも有名だ。
さて、そんな「ごん狐」について、昨日(2023年8月21日)付の「しんぶん赤旗」で、教育実践の報告記事があった(全日本教職員組合などでつくる実行委員会主催の教育研究集会における国語教育の分科会)。
小学4年生で「ごんぎつね」を読み合った授業を紹介したのは奈良県の入沢佳菜さん。物語の冒頭にある「これは、わたしが茂平というおじいさんから聞いたお話です」という文章を長い間「読み飛ばしていた」と話しました。この文章から、キツネの「ごん」の話が「村に伝わる意味」を考えたいと授業を組み立て直しました。
なお、新美の原文では次のとおりである。
これは、私が小さいときに、村の茂平というおじいさんからきいたお話です。
なるほど確かに、ごんの気持ちは、兵十にはわからないはずだ。想像するしかない。
なのに、ごんの行動や気持ちがなぜ地域に伝わっているのかを考え合いました。
これが問題設定である。
子どもたちがどう述べたのかは詳細はわからないが、一部分は次のように報じられている。
「ごんを撃ち殺したあと兵十はごんのことをわかりたかったんじゃないだろうか」「わからないところをみんなで考えて、話をつくっていって、それが茂平さんに伝わり、茂平さんが『わたし』に話し、『わたし』が自分たちに話している」と子どもたち。
「ごん狐」が正確にどういう話だったのかを思い出せない人もいるだろう。
無料で原文が読めるので、参考のためにおいておく。
兵十が遭遇した客観的事実
問題設定に付き合うとすれば、確かにごんの気持ちは兵十にはわからない。
人間側にわかる客観的事実をつないで、その間を想像で埋めたに違いない。
想像をさしはさまない、客観的事実は次のとおりである。
例えば「キツネA=キツネB」の根拠について、作中ではまともに書かれていない。
そもそも兵十がキツネAを認識したのは
兵十が、向うから、
「うわアぬすと狐め」と、どなりたてました
というところだけである。「向こう」つまり一定の距離をもってキツネAを視認していることがわかる。遠いのだ。そのように遠くから見たキツネAを、最終的にキツネBと同一だと、なぜ判断したのだろう。「尾が短い」とか「黒い斑点がある」などの描写はないのだ。
- 検察「あなたはキツネAをどこから視認しましたか」
- 兵十「川上の向こうから…50mくらい遠くからです」
- 検察「50m。50m先から視認できますか」
- 兵十「…できると思います」
- 検察「射殺したキツネBとウナギを盗んだキツネAがなぜ同一だと思ったのですか。尾が短いとか、黒い斑点があるとか、そういう識別のための何かがありますか」
- 兵十「うーん…カンのようなものですかね…。家に火縄銃があったことからもお分かりだと思いますが、私は猟師も生業としておりまして、動物の個体識別にはかなり自信があります」
- 検察「あくまで『なんとなく』ということですね」
- 弁護人「異議あり。被告は『カン』だと言っているのに誘導しています」
というような感じか。
また、射殺をされたキツネBがクリを持っていたので、土間に固めてあったクリはキツネBが運搬してきたのであろうことは一応根拠となる。ただキツネは肉食中心であり、「遊び」としてクリを山のように積んでいた可能性はないのか。クリやマツタケの前に兵十の家の前に散らばっていたイワシについても、キツネの仕業であることを立証するものは何も発見されていない。
この全体をつなげて、一つのストーリーの原型を作り出せるのは誰か。
「神様の仕業だ」というストーリーを作った加助の可能性もあるが、加助はウナギの盗難を見ていない。ウナギ盗難とクリ運搬を結びつけることができない。
したがって、このストーリーを組み立てられる唯一の人は、兵十しかいない。
だが兵十が話した素材を、加助がストーリー化した可能性はある。
兵十がストーリーを作ったか、それとも兵十+加助か。
兵十は現場で「ごん、お前だったのか」と言っていないのではないか
ぼくは、兵十の素材をもとに、加助が中心となってストーリーを作り出したと思う。
「さっきの話は、きっと、そりゃあ、神さまのしわざだぞ」「おれは、あれからずっと考えていたが、どうも、そりゃ、人間じゃない、神さまだ、神さまが、お前がたった一人になったのをあわれに思わっしゃって、いろんなものをめぐんで下さるんだよ」のような込み入ったストーリーの組み立てができるのはやはり加助ではなかろうか。兵十は「えっ?」とか「そうかなあ」とかいうだけで、およそストーリーを組み立てる能力がなさそうなのである。
ということは、たぶんキツネを射殺した直後、兵十は実際には
「ごん、お前(まい)だったのか。いつも栗をくれたのは」
という有名なセリフを現場で言ってない可能性が高い。
それは加助がストーリーに仕立て上げて、解釈を施した結果であり、民話として成立したのちに加えられたのであろう。
独り身をあわれむ
神様があわれんでクリやマツタケを届けてくれたというよりも、同じ独り身であるキツネが同情してくれた、という展開の方が、身にしみる。ウナギを盗んで台無しにしてしまい、今際の際の母親の願いを絶ってしまった贖罪の意味が込められれば、なおさらである。
兵十は今まで、おっ母と二人ふたりきりで、貧しいくらしをしていたもので、おっ母が死んでしまっては、もう一人ぼっちでした。
「おれと同じ一人ぼっちの兵十か」
こちらの物置ものおきの後うしろから見ていたごんは、そう思いました。
「ごん狐」において胸を締め付けられる箇所は、ラスト以上に、このような、ごんが兵十に対して抱く同情心の描写である。その同情は村人たちの同情そのものである。
加助が仕上げたストーリーは、家族や縁者の相互扶助が一切期待できず、誰にも頼ることができない「ひとりもの」に対する染み入るような同情、そして連帯の気持ちから、村(共同体)において急速に広がり、継承されていったに違いない。
「ごん狐」が書かれた時代
「ごん狐」が書かれたのは、福祉制度も社会保障もほとんどない1937年である。
昭和恐慌、満州事変、日中戦争が日本の農村に打撃を与えた中で、この童話は書かれた。
貧困対策法であった「恤救規則」では貧困層を全く救えずにこの体制が破綻。内務省の諮問機関が、対象を広げ、国・地方公共団体の公的扶助義務を明確にした「救護法」を答申するが、実現が頓挫しかかる。そこに、民生委員の原型である「方面委員」が運動を起こすのである。
1930年、全国の方面委員らが中心となって実施期成同盟会が結成され、議会への実施要望の陳情などの活動を展開し、天皇への上奏までを決意した。その甲斐もあって1932年1月から実施された。…地域において直接生活困窮者と接していた方面委員が組織的に活動を継続し、ついに政府を動かしたことは画期的なことであった。(井上圭壯・藤原正範『日本社会福祉史』p.8-9)
「ごん狐」は
むかしは、私たちの村のちかくの、中山というところに小さなお城があって、中山さまというおとのさまが、おられたそうです。
という封建領主がいた時代の物語である。むろん社会福祉などは一片も存在しない時代だ。
相互扶助さえ受けられぬ住民への憐憫・同情・連帯が、加助の作成したストーリーを広く村に伝え継承させた原動力になり、それを昭和恐慌に苦しむ辺境に住んでいた新美が民話として完成したのであろう。
それが
これは、私が小さいときに、村の茂平というおじいさんからきいたお話です。
と冒頭につけている理由である。どっとはらい。